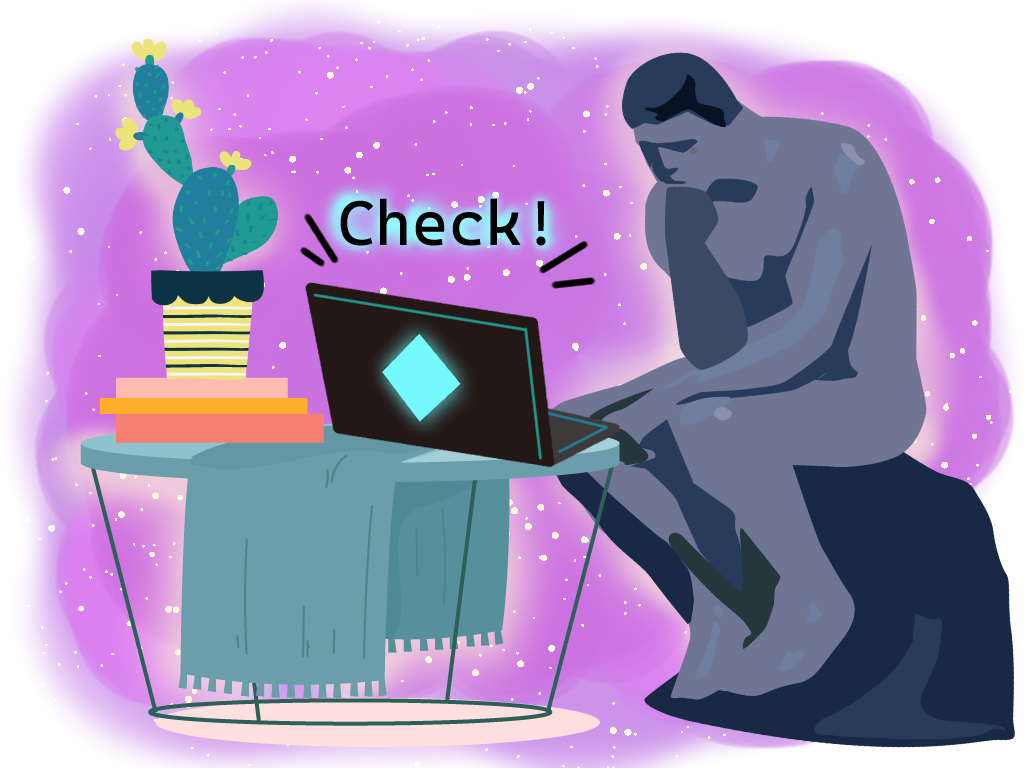平日・土曜・日祝受付中
2022/8/26 更新
【寄与分5種の計算レシピ】~計算例付~
増やせる相続遺産額いくら?
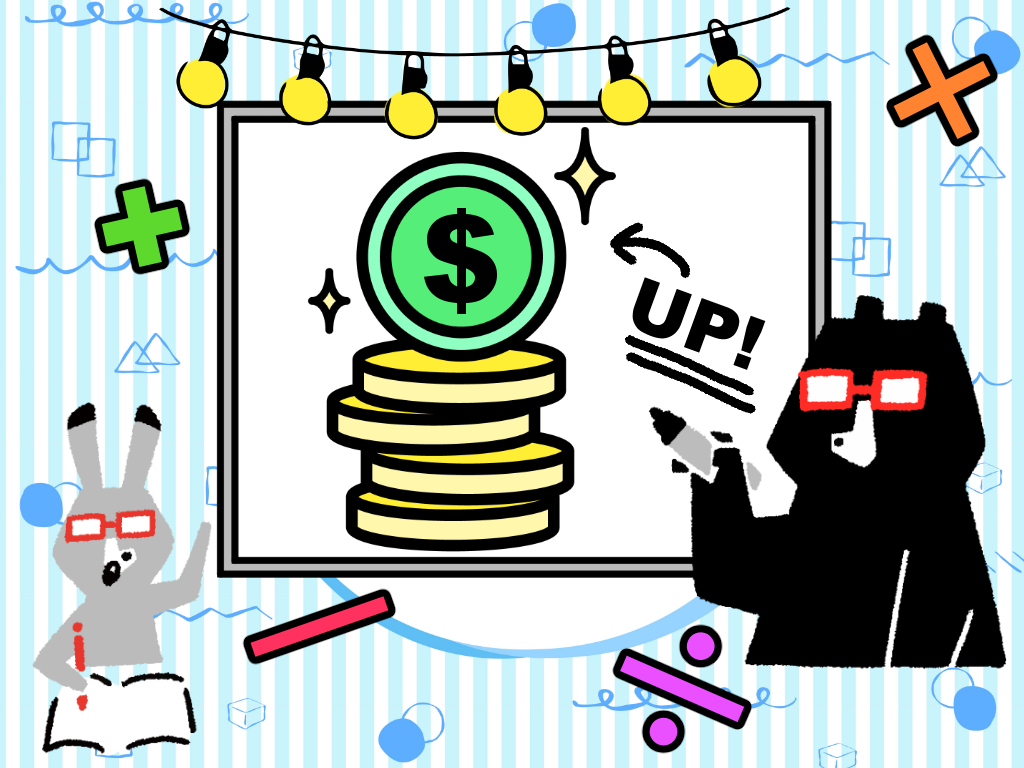
こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは「寄与分の計算方法」。
「父の事業経営のために尽くした」
「兄弟の中で唯一父の介護をし、お世話した」
生前に貢献した人の中には、他の相続人との「平等な遺産分け」に納得できない人もいるでしょう。
貢献度が高く財産形成に影響を与えていれば、寄与分を主張することで他の相続人よりも多く遺産を相続できる可能性があります。
では、具体的にいくらぐらい金額を増やせるのでしょうか?

「寄与分を主張したいけど、基準額ってどのくらい?」
「今すぐ目安金額が知りたい」
▼
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
本記事では、「5タイプの寄与分」について、それぞれ算出方法を解説しています。
主張したい寄与分に合った内容をチェックしてみましょう。
また、寄与分を反映させた「最終的な相続遺産額」の計算方法も簡単にまとめました。
必要であれば併せて参考にしてみて下さい。

・・・ この記事を読む前に ・・・
(以下の点にご留意ください。)
◆:寄与分は本来、「相続人同士で話し合って決めるもの」。
- 貢献した度合いを数値化することはとても困難です。
- 寄与分に正解は無く、統一化された明確な計算式はありません。
◆:裁判所が判断する際の基準を使えば、ある程度の目安金額は算出できる。
- 話し合いで解決できない場合、審判で寄与分額を決めてもらうことも出来ます。
- 本記事では、「裁判所式」の算出方法を解説しています。
◆:本記事の計算方法は、裁判所が使っているとされる代表例です。
- 実際は別の方法で算出されたり、調整されることがあります。
◆:あくまで「参考金額」に留め、本格的な対策は専門家へに相談を強くおすすめします。

さっそく寄与分を計算をしてみましょう。
貢献タイプ別に、「算出方法」と「計算例」をまとめました。
以下リストから当てはまる内容をチェックしてみて下さい。
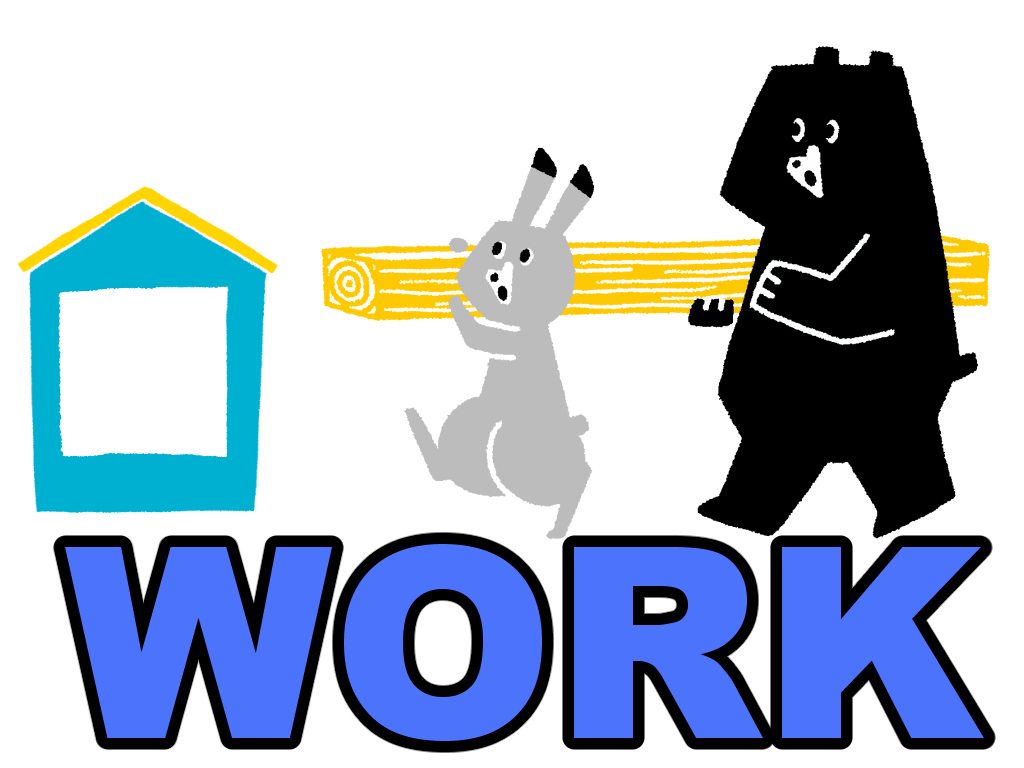
故人経営の会社で労働し、貢献していたケース。
「無報酬」または「著しく低報酬」で働いていた場合が当てはまります。
共同経営していた場合も基本的には同じ計算方法です。
通常得るべき年収額 ×( 1 - 生活費控除率)× 働いた年数
- 実際の収入額
★「通常得るべき年収額」
通常どおり給与(報酬)を得ていた場合の金額。
金額は、政府が調査・統計した賃金資料を参考にします。
★Point
同じような労働条件の賃金をチェックしましょう。
「年齢」
「性別」
「業種」
「企業規模」
★「生活費控除率」
交通事故死による損害賠償金を計算する時に使用する割合。
本来の目的とは異なりますが、生活費の算出用に参考とされています。
適用される割合は「30%~50%」。
割合を決める基準は以下のとおりです。
| 死亡した人 | 生活費控除率 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 「一家の支柱」かつ「1名を扶養」していた人 | 40% | |
| ② | 「一家の支柱」かつ「2名以上を扶養」していた人 | 30% | |
| ③ | 「支柱以外の女性」 | 30% | |
| ④ | 「支柱以外の男性」 | 50% | |
!寄与分の場合は「生きている相続人」に適用させるため、控除率を反転。(1 - 生活費控除率)
!法によって定められてはいなく、過去の裁判事例などから調整されることもあります。
★Point
生活費の「実額」を差し引く方法もあります。
(通常得るべき年収額 - 年間の生活費)
× 働いた年数 - 実際の収入額
!故人に負担してもらっていた生活費を差し引きます。
(小遣い、水道光熱費、食費、etc.)
★「実際の収入額」
僅かでも報酬を得ている場合は差し引きます。
~ 計算例 ~
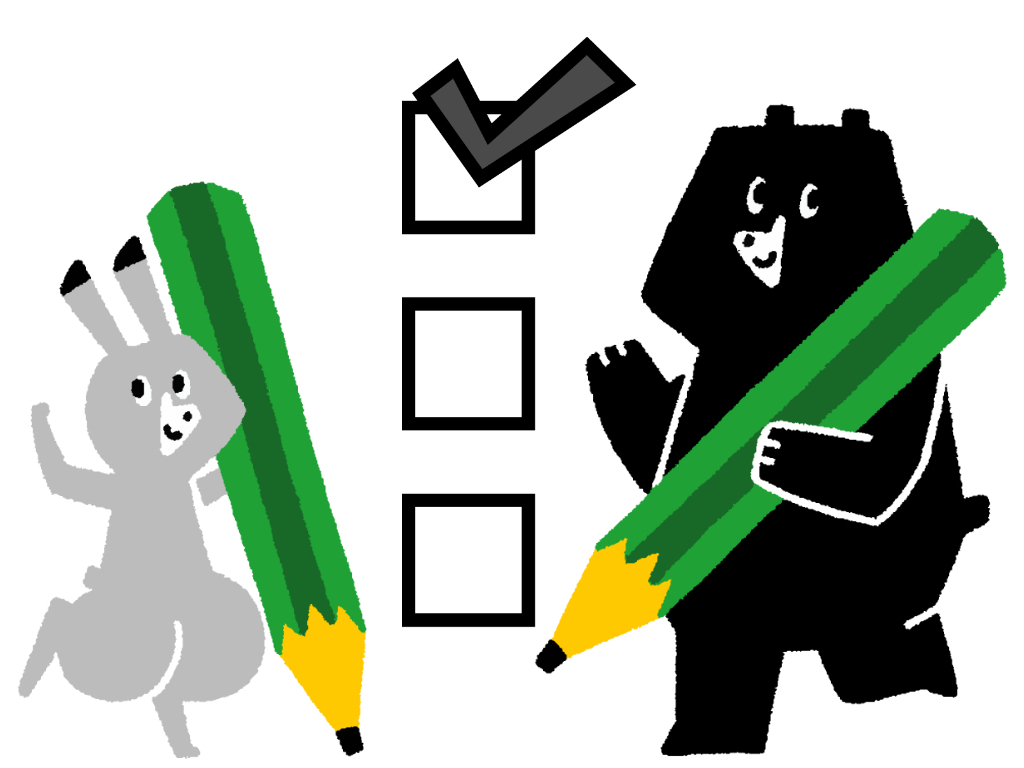
「生活費控除率」を使った場合
★通常得るべき年収額:「350万円」 |
| ★生活費控除率:「30%」 |
| ★働いた年数:「10年」 |
| ★実際の収入額:「なし」 |
「寄与分」
= 通常得るべき年収額 ×( 1 - 生活費控除率)× 働いた年数 - 実際の収入額
= 350万円 ×(1 - 0.3)× 10年 - 0円
= 2,450万円
「生活費」が分かる場合
★通常得るべき年収額:「400万円」 |
| ★生活費(年間):「180万円」 |
| ★働いた年数:「10年」 |
| ★実際の収入額:「なし」 |
「寄与分」
=(通常得るべき年収額 - 年間の生活費) × 働いた年数 - 実際の収入額
=(400万円 - 180万円)× 10年 - 0円
= 2,200万円
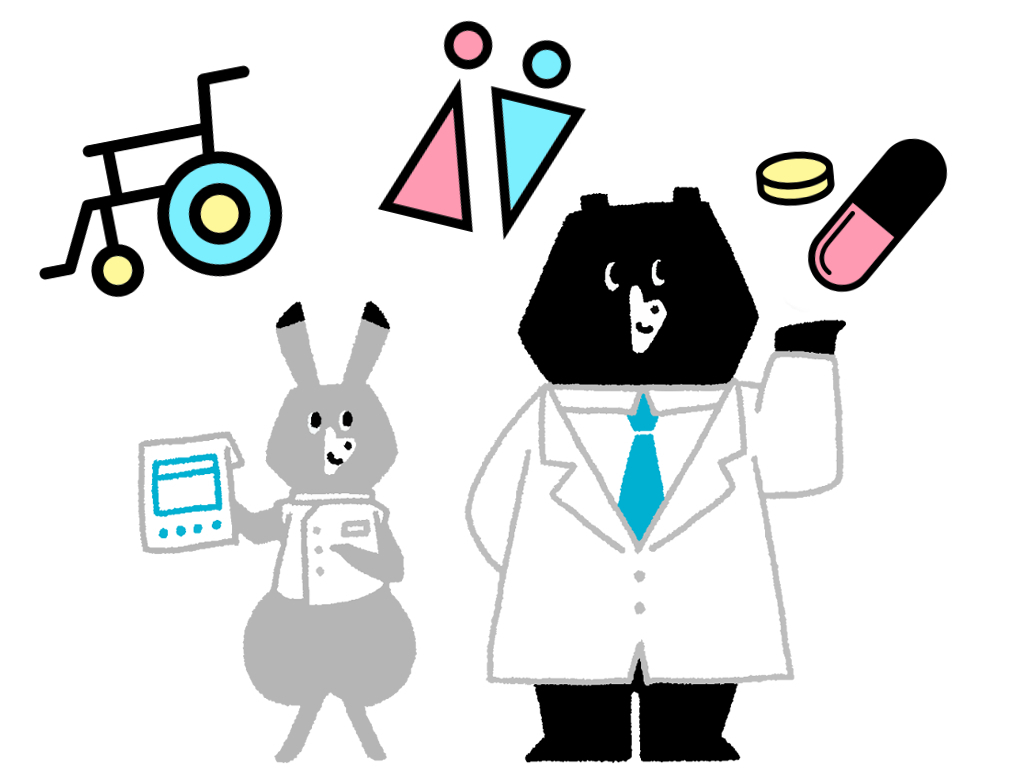
故人のお世話をし貢献していたケース。
実際に介護はせず、「金銭的負担」をしていた場合も対象となります。
「実際に介護した」場合の寄与分
1日の介護報酬相当額 × 介護日数 × 裁量的割合
「介護費用を負担」した場合の寄与分
負担した費用
★「介護報酬相当額」
介護サービスを受けていたとしたら、いくらぐらいの費用負担になるのかを計算します。
参考にするものは、介護保険制度による「介護報酬基準額」。
ただ、故人の介護レベル、介護内容や地域などによって細かく設定されており、確定が難しいかもしれません。
目安金額が簡単に分かる、厚生労働省の計算サイトがおすすめです。
★「介護日数」
実際に介護した日数。
入院期間や施設入所期間、介護サービスを受けた期間は原則除きます。
★「裁量的割合」
内容を吟味し、裁判所が最終的に調整するための割合。
事情を考慮して判断するため差が出ますが、「50%~80%」の値で調整されることが多いようです。
~ 計算例 ~
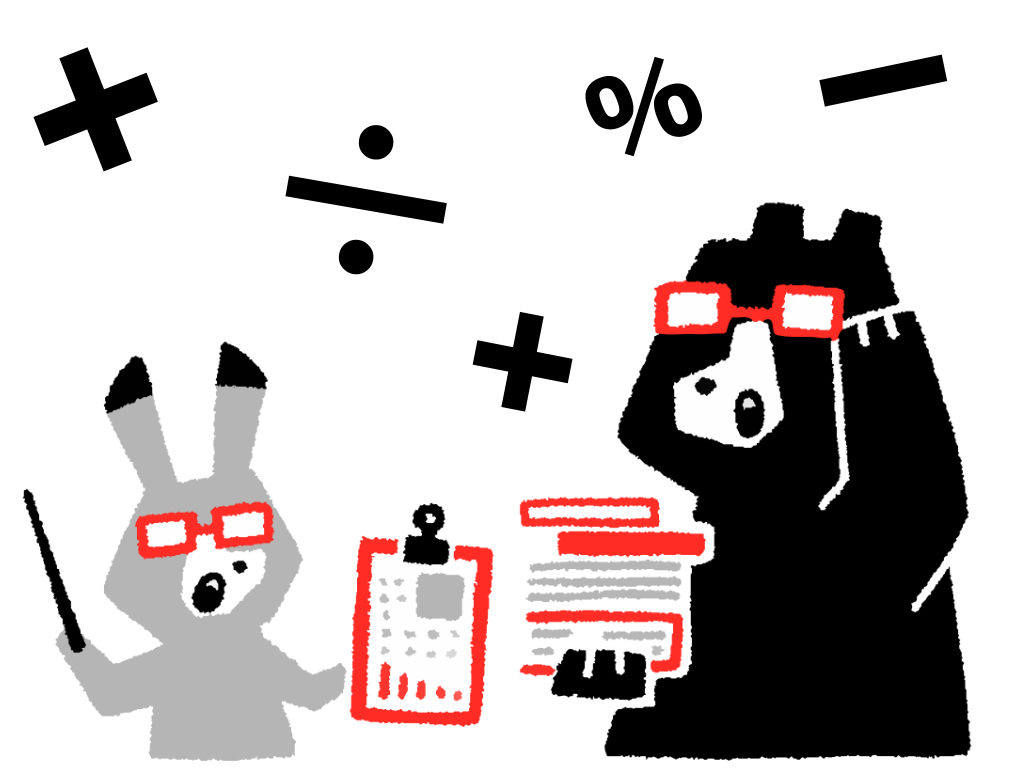
★1日の介護報酬相当額:「6,000円」 |
| ★介護日数:「100日」 |
| ★裁量的割合:「50%~80%」 |
「寄与分」
= 1日の介護報酬相当額 × 介護日数 × 裁量的割合
= 6,000円 × 100日 × 0.5~0.8
= 30万円~48万円

故人の事業や生活を援助していたケース。
会社(法人)に対して出資した場合は原則認められないため注意しましょう。
なお、「介護」や「扶養」のための資金援助については、以下タイプをチェックしてみて下さい。
「金銭」を援助した場合
援助した金額 × 貨幣価格変動率 × 裁量的割合
「不動産購入のための資金」を援助した場合
相続開始時の不動産価格 ×(援助した金額 ÷ 購入時の不動産価格)
「不動産」を贈与した場合
相続開始時の不動産価格 × 裁量的割合
「不動産を無料で貸与」した場合
相続開始時の賃料相当額 × 貸した年数 × 裁量的割合
★「貨幣価格変動率」
過去の1万円と現在の1万円の価値は、イコールではありません。
援助した時のお金の価値を、「現在」の価値に置き換える必要があります。
お金の価値を決める代表的な基準は、「消費者物価指数(CPI)」。
詳細な解説は割愛しますが、スグに目安金額が換算できる自動計算サイトを利用すると便利です。
基本的な考え方を身に付けたい人は、日銀の解説が分かりやすいためチェックしてみましょう。
★「相続開始時点の不動産価格」
土地や建物の評価額。
専門性が求められるため自己判断は難しく、通常は鑑定業者へ依頼します。
実際は状態を見て細かく調整されますが、おおよその金額であれば、「固定資産税の課税明細書」で確認できます。
紛失した場合は、役場へ問い合わせてみましょう。
★「裁量的割合」
内容を吟味し、裁判所が最終的に調整するための割合。
事情を考慮して判断するため差が出ますが、「50%~80%」の値で調整されることが多いようです。
~計算例~
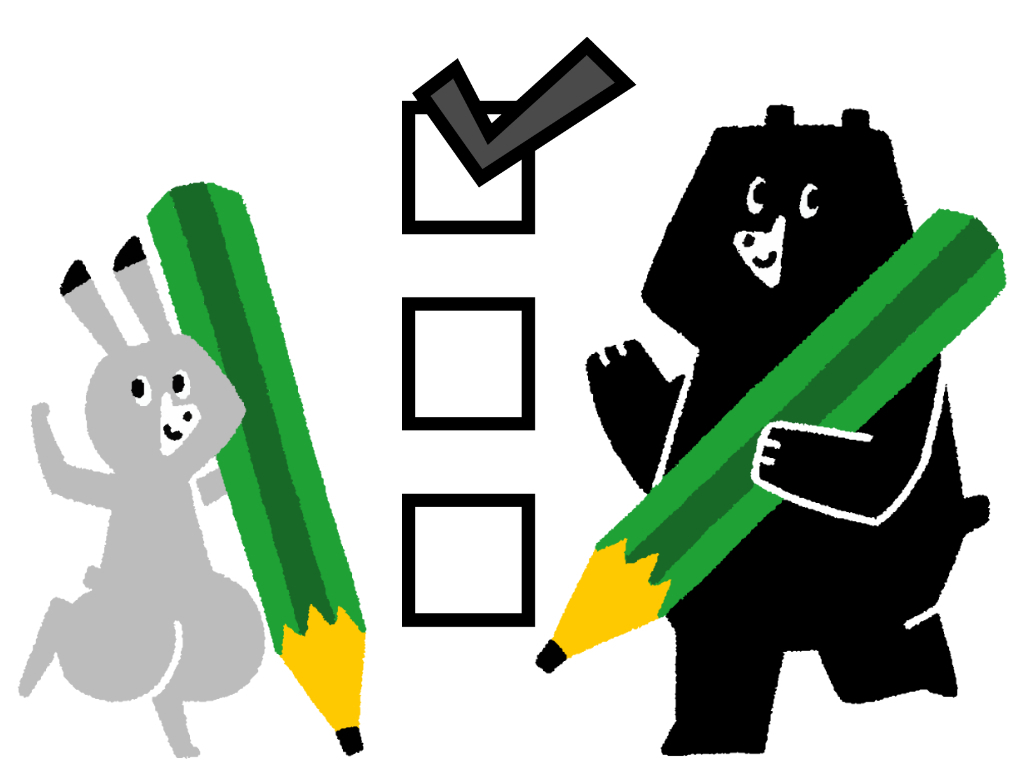
「金銭」を援助
| ★援助した金額:「1,000万円」 ※2000年に援助 |
| ★貨幣価格変動率:(自動換算使用により省略) |
| ★換算額:「1,043万円」 ※相続発生2022年 ※今回は1万円未満切り捨て |
| ★裁量的割合:「50%~80%」 |
「寄与分」
= 現在に換算した援助額 × 裁量的割合
= 1,043万円 × 0.5~0.8
= 521.5万円~834.4万円
「不動産購入のための資金」を援助
| ★援助した金額:「2,000万円」 |
| ★相続開始時の家の価格:「1,000万円」 |
| ★購入時の家の価格:「2,500万円」 |
「寄与分」
= 相続開始時の不動産価格 ×(援助した金額 ÷ 購入時の不動産価格)
= 1,000万円 × (2,000万円 ÷ 2,500万円)
= 800万円
「不動産」を贈与
| ★相続開始時の土地価格:「1,500万円」 |
| ★裁量的割合:「50%~80%」 |
「寄与分」
= 相続開始時の不動産価格 × 裁量的割合
= 1,500万円 × 0.5~0.8
= 750万円~1,200万円
「不動産を無料で貸与」
| ★相続開始時の賃料相当額(年額):「84万円」 |
| ★貸した年数:「10年」 |
| ★裁量的割合:「50%~80%」 |
「寄与分」
= 相続開始時の賃料相当額 × 貸した年数 × 裁量的割合
= 84万円 × 10年 × 0.5~0.8
= 420万円~672万円
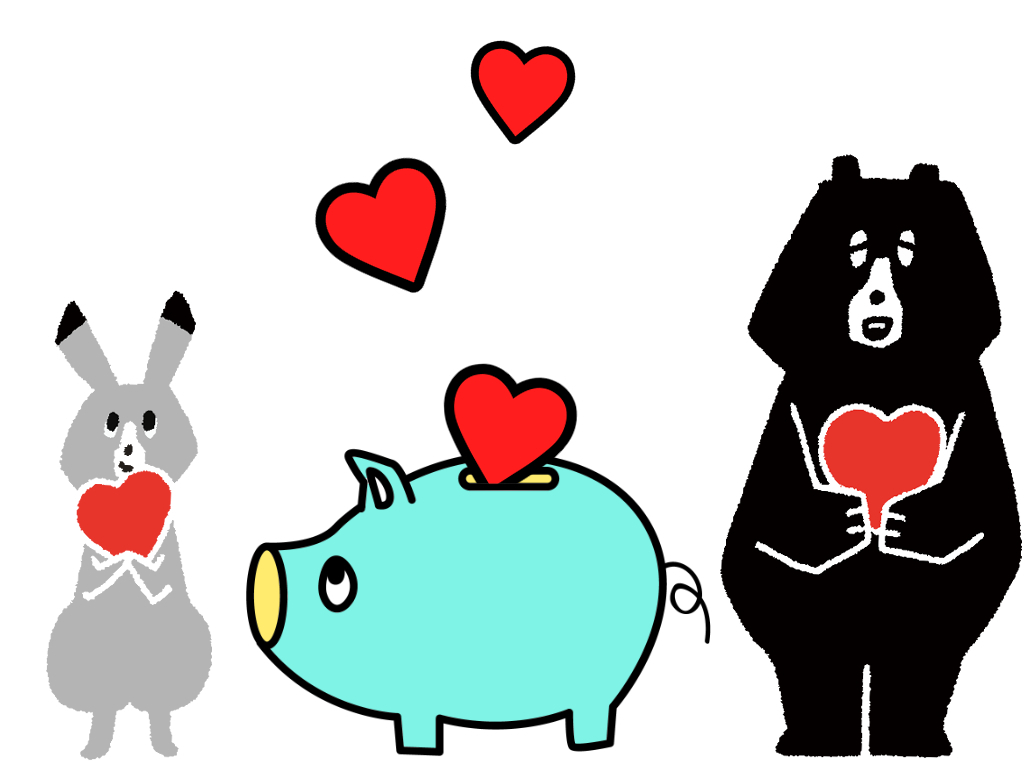
故人を養うことで貢献したケース。
別居、同居どちらも対象となります。
「仕送りで扶養」していた場合
仕送り金額 ×( 1 - 寄与分を主張する人の法定相続分)
「一緒に住んで扶養」していた時
負担額 × 扶養期間 ×( 1 - 寄与分を主張する人の法定相続分)
★「法定相続分」
法律で決められている遺産の取り分。
遺言書がない場合などに適用され、相続人の組み合わせで決まります。
法定相続分が分からない人は、以下記事で診断できますのでチェックしてみて下さい。
★「負担額」
負担額が分からない時は、「生活保護基準額」を参考に計算することもできます。
生活保護基準額 × 扶養期間
×( 1 - 寄与分を主張する人の法定相続分)
自動計算してくれる以下サイトがおすすめです。
~ 計算例 ~
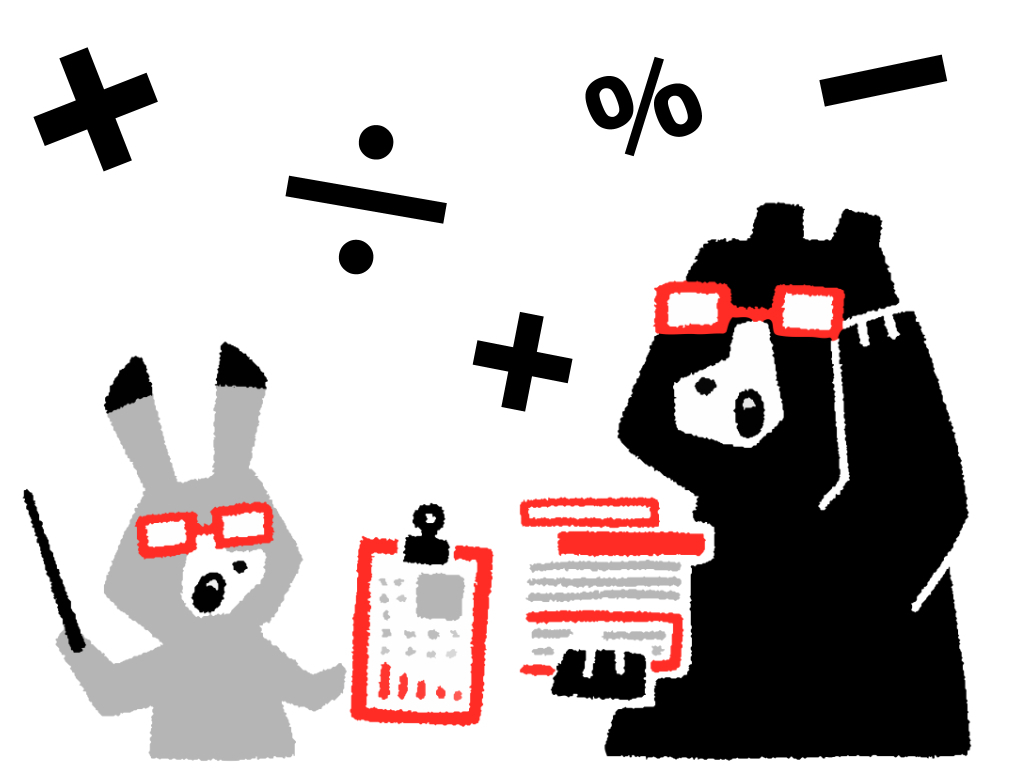
「仕送りで扶養」
★仕送り金額:「300万円」 |
| ★寄与分を主張する人の法定相続分:「1/3」 ※相続人が子3人の場合 |
「寄与分」
= 仕送り金額 ×( 1 - 寄与分を主張する人の法定相続分)
= 300万円 ×(1 - 1/3)
= 200万円
「一緒に住んで扶養」
★負担額:「600万円」 |
| ★扶養期間:「5年」 |
| ★寄与分を主張する人の法定相続分:「1/3」 ※相続人が子3人の場合 |
「寄与分」
= 負担額 × 扶養期間 ×( 1 - 寄与分を主張する人の法定相続分)
= 600万円 × 5年 ×(1 - 1/3)
= 2,000万円

故人の財産をお世話して貢献したケース。
賃貸不動産の管理や土地を売る際の売買契約、交渉などが対象となります。
第三者に委任した場合の費用 × 裁量的割合
★「第三者に委任した場合の費用」
専門家などに依頼した場合に想定される、報酬や仲介手数料。
★「裁量的割合」
内容を吟味し、裁判所が最終的に調整するための割合。
事情を考慮して判断するため差が出ますが、「50%~80%」の値で調整されることが多いようです。
~ 計算例 ~
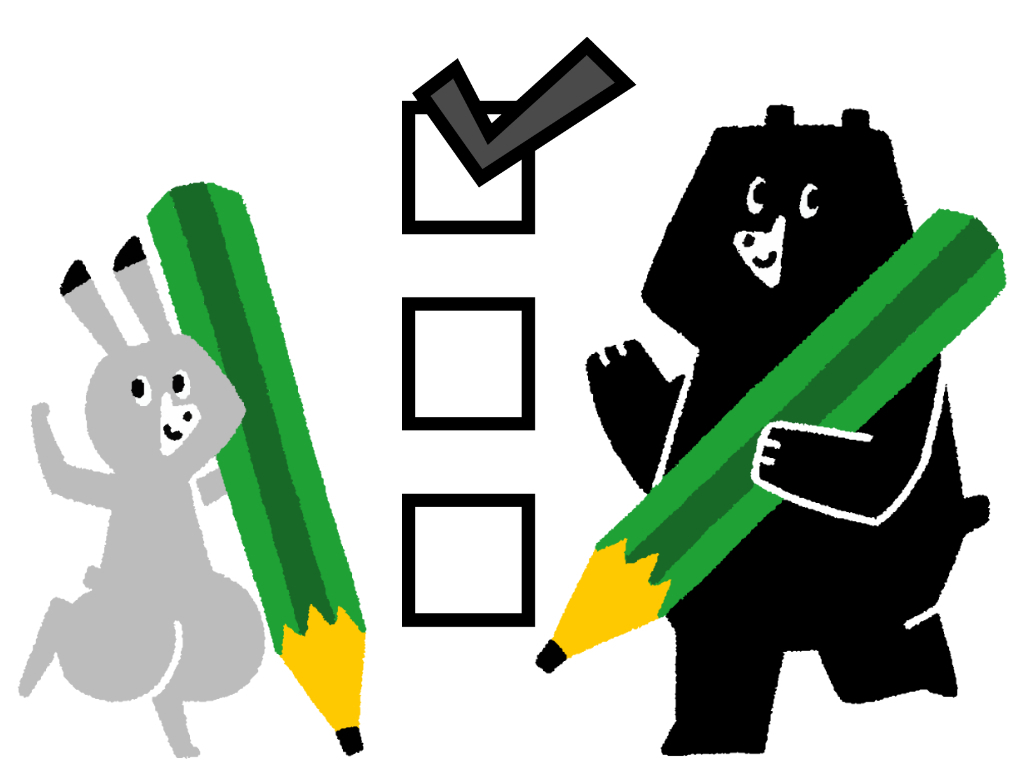
| ★土地売却を不動産会社に依頼した場合の費用:「150万円」 |
| ★裁量的割合:「50%~80%」 |
「寄与分」
= 第三者に委任した場合の費用 × 裁量的割合
= 150万円 × 0.5~0.8
= 75万円~120万円
★・寄与分反映させた相続遺産額・★

寄与分を含めた、最終的な相続額の求め方は以下のとおり。
他の相続人も同様に計算します。
★step.①
遺産額 - 寄与分
★step.②
step.① × 法定相続分
★step.③
step.② + 寄与分
★「寄与分」
★「法定相続分」
法律で決められている遺産の取り分。
遺言書がない場合などに適用され、相続人の組み合わせで決まります。
法定相続分が分からない人は、以下記事で診断できますのでチェックしてみて下さい。
~ 計算例 ~
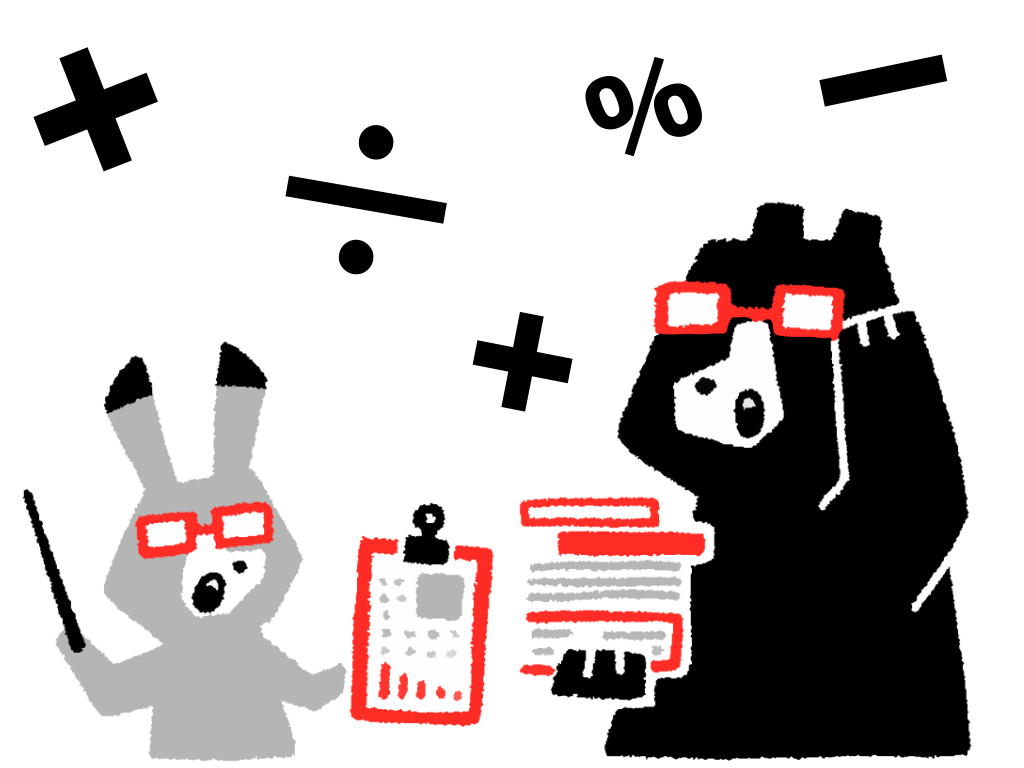
| ★遺産額:「5,000万円」 |
| ★寄与分を主張する人の法定相続分:「1/4」 (※相続人が配偶者、子2人の場合) |
| ★寄与分:「500万円」 |
★step.①
遺産額 - 寄与分
= 5,000万円 - 500万円
= 4,500万円
★step.②
step.① × 法定相続分
= 4,500万円 × 1/4
= 1,125万円
★step.③
step.② + 寄与分
= 1,125万円 + 500万円
= 1,625万円
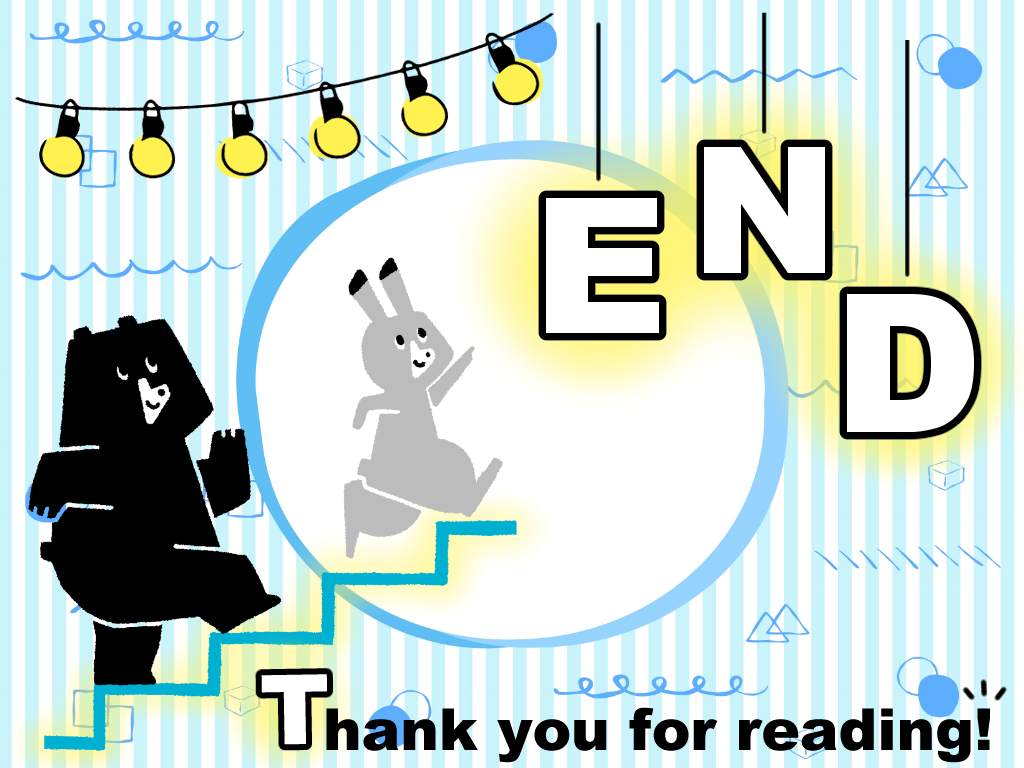
今回紹介した計算方法を使えば、寄与分の目安金額を知ることができます。
「モノサシ」があれば、寄与分主張もし易くなるかもしれませんね。
とは言え、寄与分は必ずしも認められるわけではありません。
とくに裁判所で判断してもらうことになる場合は「証拠」が必要不可欠であり、慎重な対策が必要です。
どれだけ貢献していたとしても、寄与分が成立しない可能性がある点に注意しましょう。
不安な人やしっかり対策をしたい人は、やはり専門家への相談をおすすめします。
当事者だけでの解決が難しいと思った場合は、前向きに検討してみましょう。
相談するならまずは「無料相談」からでOK。
何件か連絡し、信頼できそうな相手が見つかったら依頼する形で問題ありません。
それでも相談先が見つからず、お困りの方やお急ぎの方。
ぜひ一度ご相談ください。
【Pick up!】こちらの記事もCheck!
【動画チャンネル】
税制の改正や相続に関する情報をタイムリーに配信中!
是非登録してくださいね!
税金!相続等の情報をタイムリーに
解りやすく動画で配信しております!
ぜひチャンネル登録をしてご覧ください
youtubeのテーマ募集中!
- 【朗報】持続化給付金、税理士の売上確認、署名が「無料」に!?【個人事業主やフリーランスの申請】
- 半沢直樹の第1〜4話にみる【債権放棄】とは?【税理士が詳しく解説】