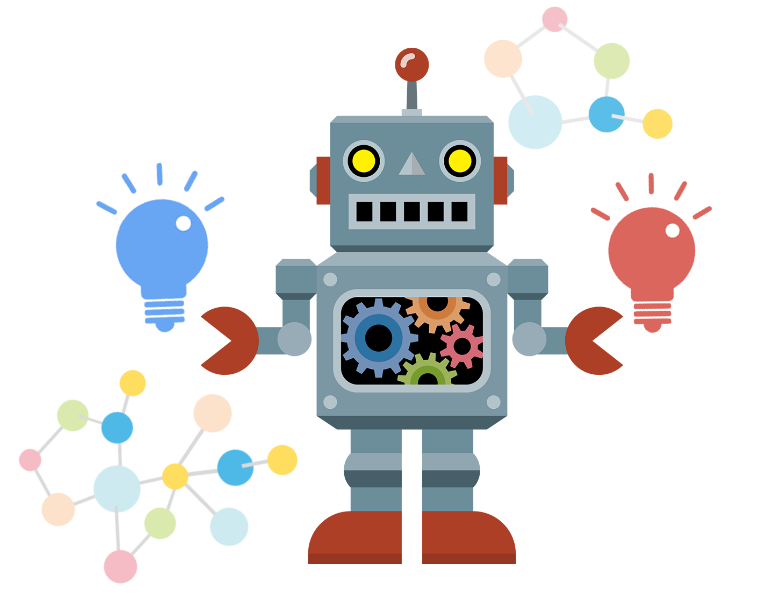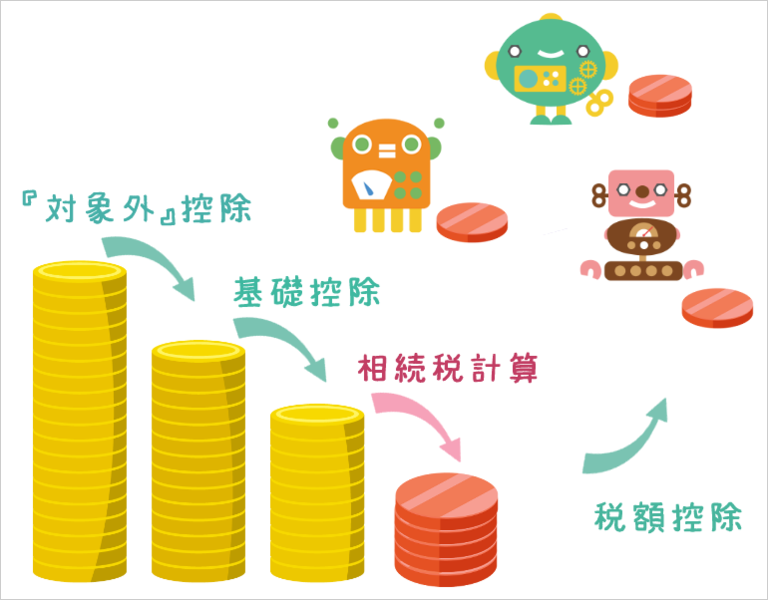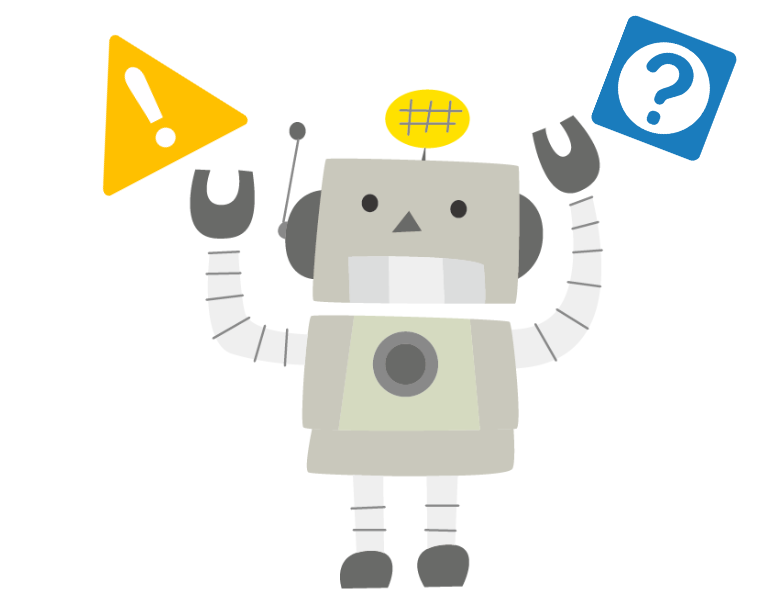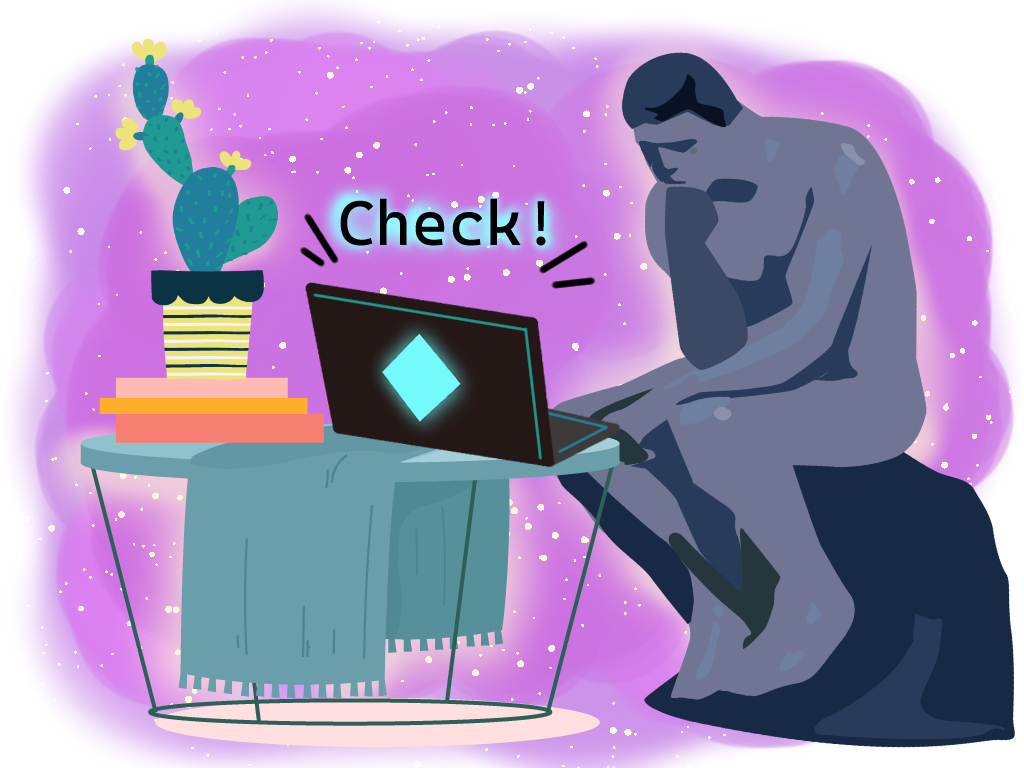平日・土曜・日祝受付中
2021.1.26(↻2022.1.27更新)
相続税の対象外!非課税な控除財産って? 減税制度7つもご紹介
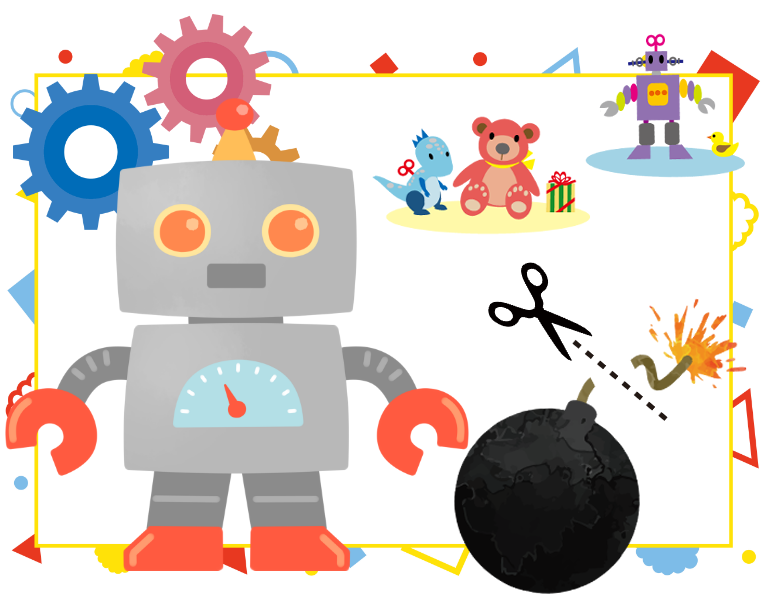
こんにちは!相続税理士の天尾です。('ω')
今回のテーマは相続税がかからない『控除対象』の財産。
相続税は、単に受け継いだ財産だけで計算されるわけではないのです!

「相続税がかからない財産って?」
「お得にできる制度が知りたい!」
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
さらに、知らなきゃ損する相続税の『控除制度』もご紹介。
知らないまま相続税を多く支払うなんて、勿体ないですよね。
納める相続税が不足しているのは問題ですが、何も余分に支払う必要はありません。
削れる部分は遠慮なく削り、徹底的にお得にしていきましょう!
その①
【マイナス財産】&【葬式費用】
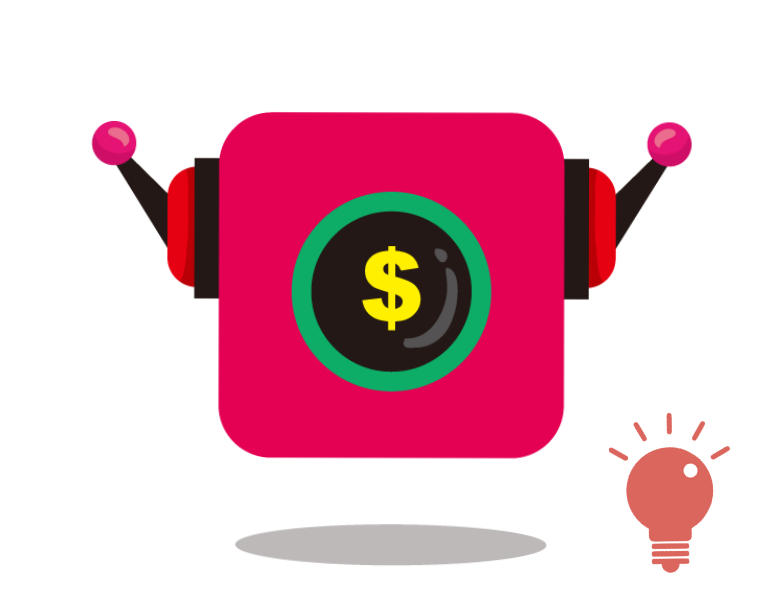
故人の負債や未払い金、葬式費用は課税対象外。
相続財産から引き、残った財産にだけ相続税が発生します。
◆:負債・未払い
- 銀行からの借入金
- 個人的な借金
- 未払いの医療費
- 固定資産税や住民税、所得税
◆:葬式費用
- 通夜~納骨までの葬儀一式費用
- 遺体搬送費用
- 葬儀関連の飲食費
- お布施
- 心づけ

▲・Check!・▲
【『対象外』の対象外もある】
財産額から差し引くことができないものもあります。
混同しないように注意しましょう。
- 故人の『生前中に』支払った医療費
- 故人の『生前中に』料金が確定し、請求されている各種料金
- 香典返し
- 生花、盛籠
- 墓石、仏壇、位牌の購入費用
- 初七日、四十九日の法事費用
その②
【プラス財産】
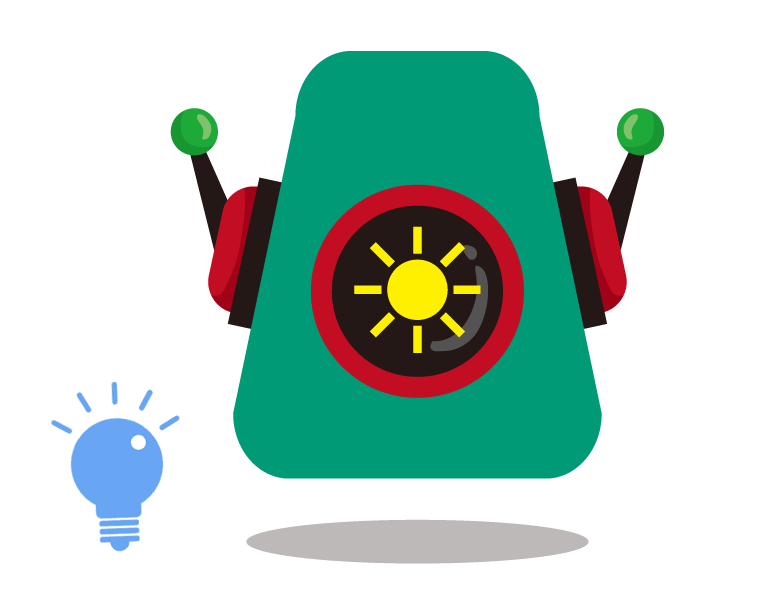
プラス財産でも相続税がかからないものがあります。
対象外は3種類。
詳細は以下のとおりです。
◆:死亡保険金
死亡保険金には『非課税枠』が用意されており、枠内に収まれば相続税はゼロ。
はみ出た部分のみ課税対象となります。
◆・非課税枠・◆
500万円 × 法廷相続人の数
◆:【受け取った生命保険金】5,500万円
◆:【法定相続人】3人
500万円 × 3人 = 1,500万円
5,500万円 - 1,500万円 = 4,000万円
『4,000万円』が課税対象
◆:死亡退職金
死亡保険金と同じように、『非課税枠』が用意されています。
枠内を超えた部分のみ課税対象です。
◆・非課税枠・◆
500万円 × 法廷相続人の数
◆:【受け取った死亡退職金】700万円
◆:【法定相続人】2人
500万円 × 2人 = 1,000万円
700万円 < 1,000万円
相続税の対象外
◆:先祖を祭る礼拝物
- お墓
- 墓地
- 仏壇
- 仏具
- 神具
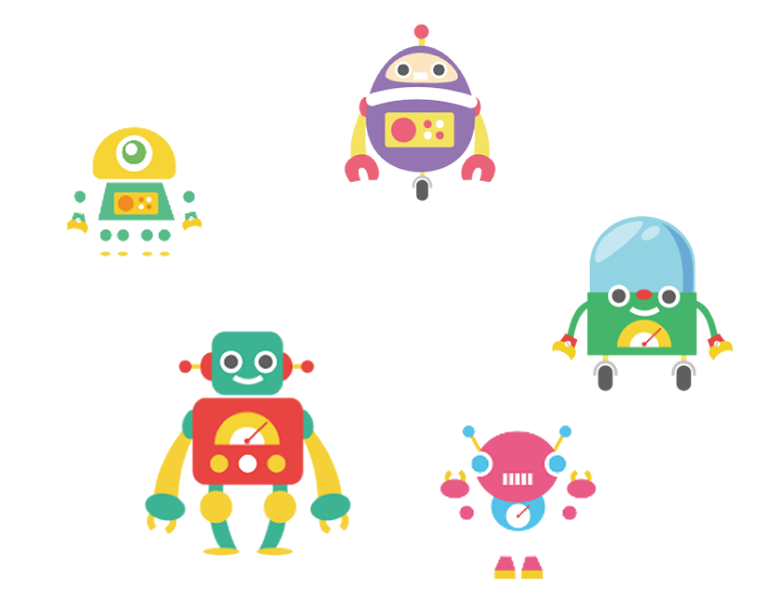
相続人であれば誰でも使える基本的な控除。
相続税の計算は、基礎控除でトータル財産額を減らすことから始めます。
財産額が基礎控除額以内であれば、相続税はゼロです。
【基礎控除額】
3,000万円 + 600万円 × 法廷相続人の数
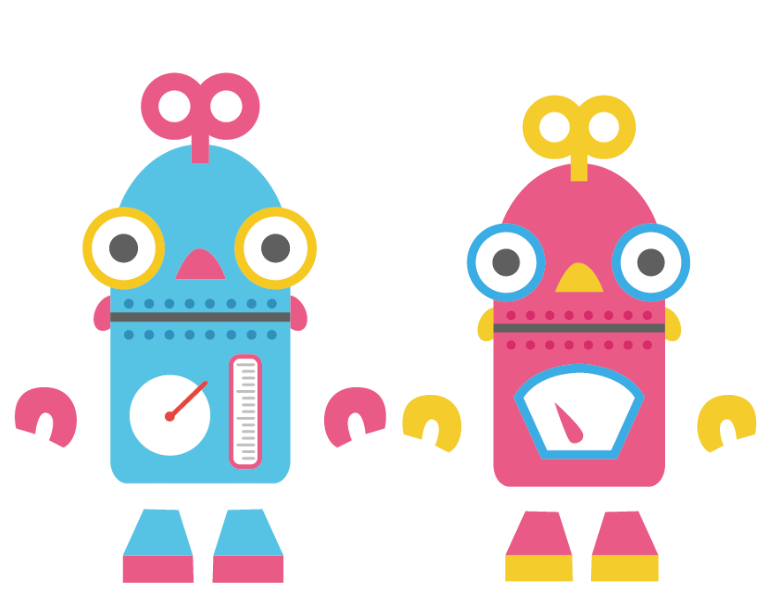
故人の妻や夫が使える控除制度。
内縁の妻や夫、愛人などは使うことが出来ません。
算出された相続税額から差し引きます。
【控除額】
1億6,000万円までの相続税
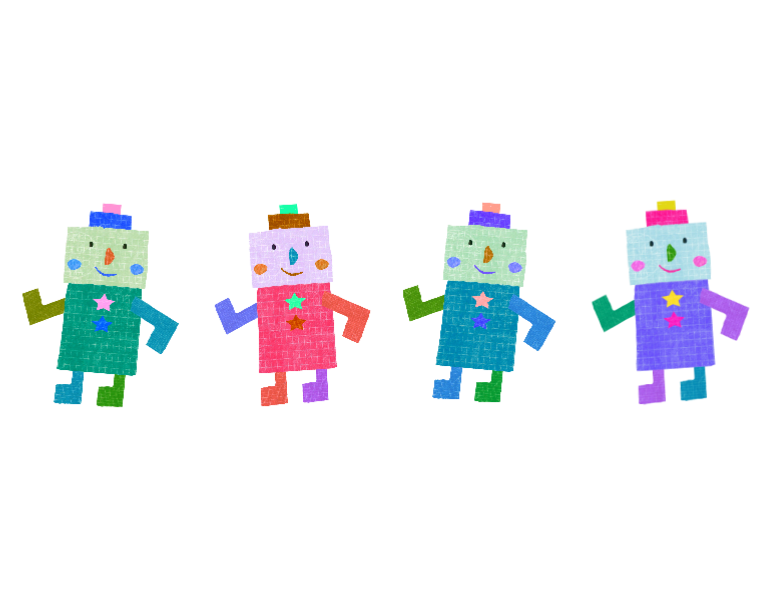
20歳未満の相続人が使える控除制度。
相続した時点で未成年者であることが条件です。
算出された相続税額から差し引きます。
【控除額】
20歳になるまでの年数 × 10万円
◆:計算例(相続人の年齢が12歳のとき)
【20歳になるまでの年数】
= 20 - 12
= 8年
【控除できる相続税額】
= 8年 × 10万円
= 80万円
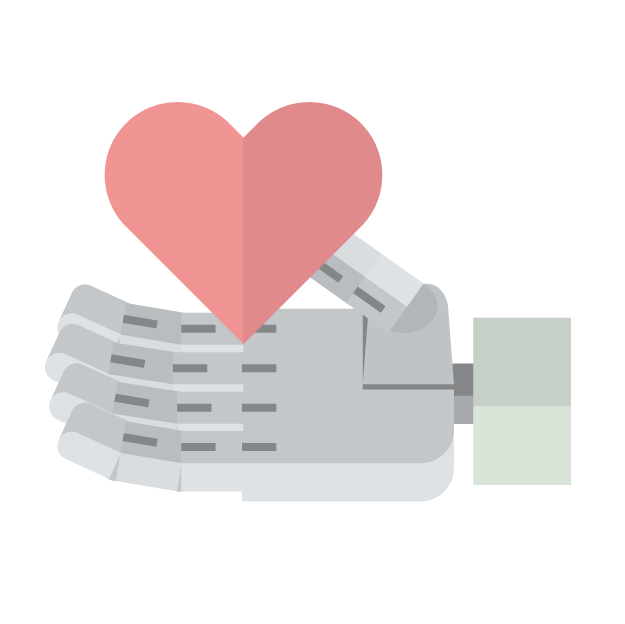
相続人が障害者や特別障害者の場合に使える制度。
相続した時点で障害者であることが条件です。
算出された相続税額から差し引きます。
【『障害者』の控除額】
85歳になるまでの年数 × 10万円
【『特別障害者』の控除額】
85歳になるまでの年数 × 20万円
◆:計算例(相続人の年齢が30歳のとき)
【85歳になるまでの年数】
= 85 - 30
= 55年
【控除できる相続税額】
◆:障害者の場合
= 55年 × 10万円
= 550万円
◆:特別障害者の場合
= 55年 × 20万円
= 1,100万円
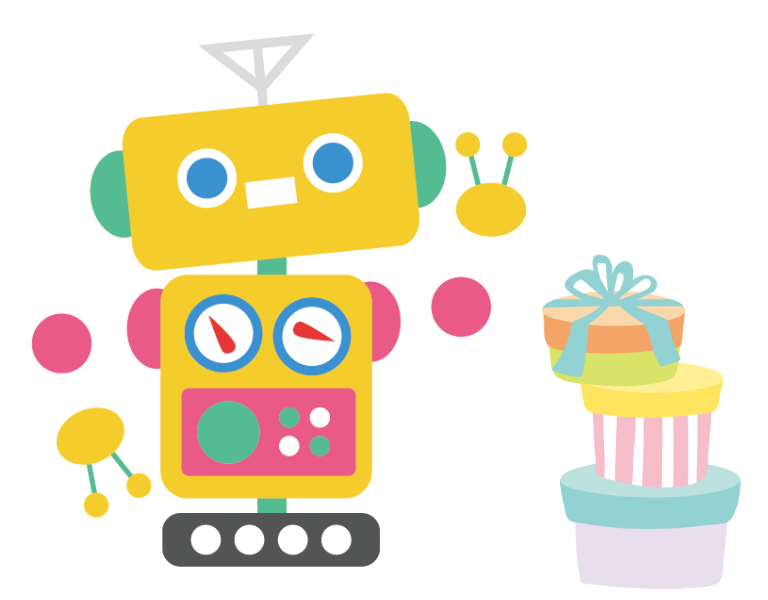
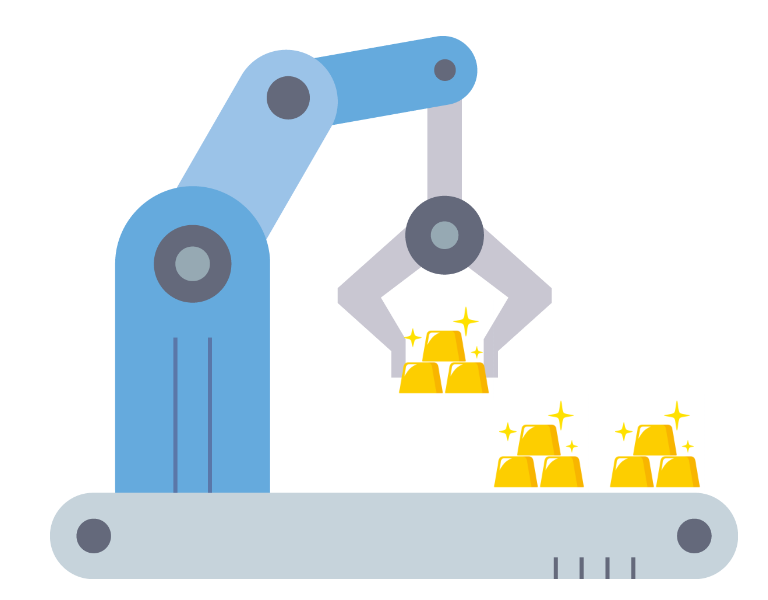
故人が以前の相続で取得した財産が、今回の相続財産である時に使える制度。
連続で相続財産が動いている場合に適用されます。
条件としては大きく2つ。
◆:前回の相続~今回の相続までの期間が『10年以内』
◆:故人が以前の相続で、相続税が課税されている
【控除額】
A × C/B-A × D/C ×(10-E)/10
【A】故人が『前回の相続』で支払った相続税
【B】故人が『前回の相続』で取得した純資産価額
【C】『今回の相続』の純資産価額の合計
【D】『今回の相続』で取得した、相続人それぞれの純資産価額
【E】前回の相続~今回の相続までの期間
※純資産価額とは、プラスの財産から債務や葬式費用を引いた金額
※前回の相続からの経過期間については、1年未満は切り捨て
◆:計算例
【亡くなった人】:祖父
【相続開始日】:令和4年2月1日
【相続人】:子2人(父、父の弟)
【純資産価額】:1億円
【父が相続した純資産価額】:5,000万円
【父が支払った相続税】:385万円
【亡くなった人】:父
【相続開始日】:令和6年4月1日
【相続人】:子2人(子1、子2)
【純資産価額】:2憶円
【子1が相続した純資産価額】:1億2,000万円
【子2が相続した純資産価額】:8,000万円
【A】385万円
【B】5,000万円
【C】2憶円
【D】1憶2,000万円
【E】2年(1年未満切り捨て)
◆:控除額
= 385万円 × 2億円 /(5,000万円 - 385万円)
× 1憶2,000万円 / 2億円 ×(10 - 2年)/ 10
= 385万円 × 2億円 / 4,615万円 × 0.6 × 0.8
= 約800万円
【A】385万円
【B】5,000万円
【C】2憶円
【D】8,000万円
【E】2年(1年未満切り捨て)
◆:控除額
= 385万円 × 2億円 /(5,000万円 - 385万円)
× 8,000万円 / 2億円 ×(10 - 2年)/ 10
= 385万円 × 2億円 / 4,615万円 × 0.4 × 0.8
= 約533万円

海外にある財産を相続した時に使える控除制度。
日本で課税される相続税を減らすことができます。
海外に対し相続税を支払っていることが条件。
【控除額】
※(少ない方の金額が適用)
①海外へ支払った相続税額
②日本での相続税額 × 相続した海外の財産割合
【相続した海外の財産割合】= 海外の財産額 ÷ 全財産額
◆・計算例・◆
【相続した日本の財産額】5億円
【相続した海外の財産額】5億円
【海外で支払った相続税】1億円
【日本での相続税】1億5,000万円
◆:①海外へ支払った相続税額
= 1億円
◆:②日本での相続税額 × 相続した海外の財産割合
= 1億5,000万円 × (5億円 ÷ 10億円)
= 7,500万円
◆:控除額
= ① > ②
= 7,500万円

相続した財産を、国や特定の地方公共団体などに寄付した時に使える控除制度。
所得税や住民税も減額できます。
【控除額】
寄付した相続財産額 × 相続税率
◆:【相続税率】= 課税対象となる遺産総額を基にした税率
- 対象外財産の控除、基礎控除をした後の残りの遺産額が課税対象額
- (例)課税対象の遺産総額が4,000万円のときの税率は20%
◆・計算例・◆
【寄付した相続財産額】300万円
【課税対象の遺産総額】8,000万円
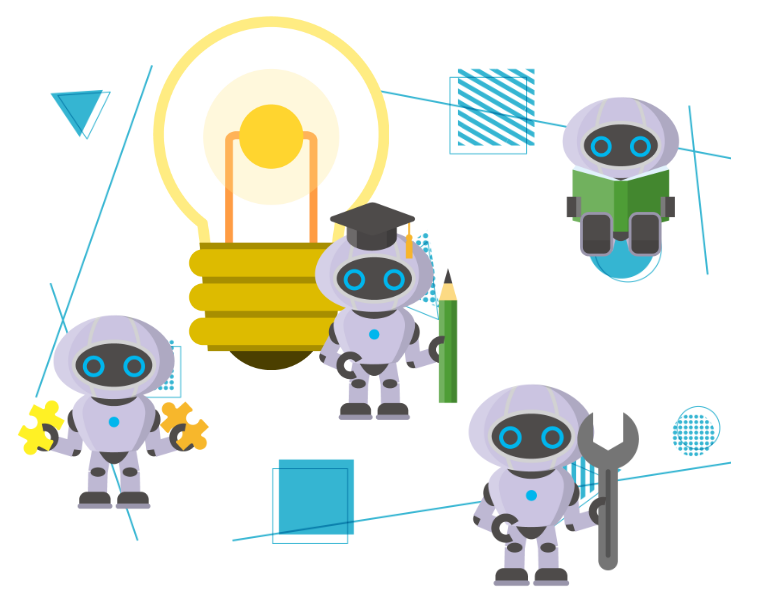
- 故人の【借金】【葬式費用】は相続税の対象外
- 非課税枠内の【生命保険金】や【死亡退職金】は相続税の対象外
- 【墓】や【仏壇】など、先祖を祭るためのものは相続税の対象外
- 【税額控除】をしっかり適用させることで、相続税を減額できる
- 相続税を過払いした時は、期限内に手続きすれば返してもらえる
少しとっつきにくい税金の話。
今回の記事で、少しだけ相続税を知ってもらえたら嬉しく思います。
相続税の申請や手続きは、もちろん皆さん自身で行うことは可能です。
しかし、計算ミスなどで申告漏れがあった場合はペナルティ。
不足分に加え、追加で税金を支払わなくてはいけません。
◆:「いろんな制度があり過ぎて、把握しきれない」
◆:「自分たちだけで対応できるか不安」
◆:「どうすれば一番お得に相続が終えられるか知りたい」
相続での悩み、アドバイスが必要な方は一度専門家へ相談してみましょう。
とくに、節税したい人やトラブル回避したい人は必須級。
自力では難しい、あらゆる問題を効率よく解決できるでしょう。
まずは無料相談を利用し、様子を見てみるのも一つの手。
信頼できそうであれば正式に依頼し、対策していきましょう。
【Pick up!】こちらの記事もCheck!
【動画チャンネル】
税制の改正や相続に関する情報をタイムリーに配信中!
是非登録してくださいね!
税金!相続等の情報をタイムリーに
解りやすく動画で配信しております!
ぜひチャンネル登録をしてご覧ください
youtubeのテーマ募集中!
- 【朗報】持続化給付金、税理士の売上確認、署名が「無料」に!?【個人事業主やフリーランスの申請】
- 半沢直樹の第1〜4話にみる【債権放棄】とは?【税理士が詳しく解説】